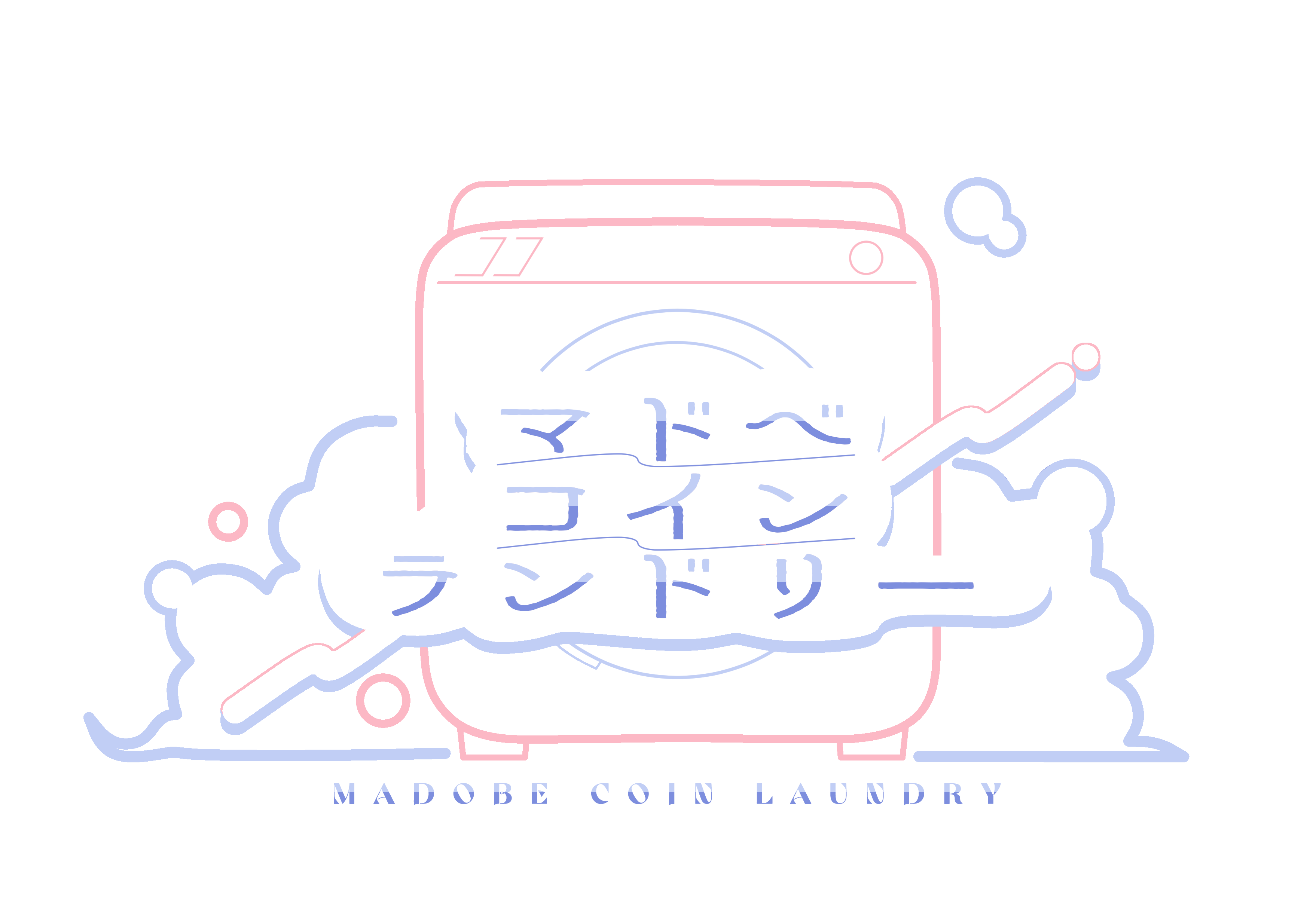飼い主の女が死んだ。長いヒモ生活の中で、痛烈なビンタで以て別れを告げられたことは幾度もあれど、死なれるのは初めてだった。
「ってわけで、死のうと思うんですよね」
「はあ」
タクシーの運転手の女は淡々とそう返し、ハンドルを左に回した。淡々と返すような内容だったかね、今のは。とはいえ、俺の話もたまたま捕まえただけのタクシーの運転手に話すようなものではなかったから、お互い様かもしれない。下手に同情的な態度を取られたり、命の大切さを道徳的に説かれたりするよりはずっとマシでもある。その他人に対する心地の良い冷たさや、ここからいちばん近い樹海まで、と言い出した客に対して事情のひとつも聞かない淡白さは、霧子に少し似ている気がした。霧子は静謐な冬の朝みたいな女だった。誕生日も冬、俺が霧子に拾われたのも冬、ああでも、死んだのは夏か。
話してもいいっすか、と、気づけばそう口にしていた。霧子に似た女の、霧子に似た温度に、なんとなくそういう気持ちになった。そういう気持ちとは要は、自分の感情の質量を、少しだけ誰かに渡してしまいたい、という気持ちのことだ。はい、と女は、やっぱり淡々と言った。
「別に、悲しいから死にたいとかじゃないんですよ。シンプルに資金源がなくなっちゃったから、これから生きていけないし、じゃあ死ぬか、みたいな感じで」
言いながらあまりのどうしようもなさに笑えてきてしまったけれど、紛れもない事実だった。ここ数年間は霧子が家賃を納める家に住み、霧子が作った飯を食い、霧子が与える服を着て生きてきた。お手本みたいなヒモだ。今はまだ霧子の家に住んでいるが、悲しみのあまり死んだ恋人の部屋からいつまでも離れられない憐れな男をやるのもそろそろ限界だろう。霧子の両親も、まさか娘の部屋にいる男が娘の恋人ではなく娘のヒモで、恋人を悼むから電球が切れかかっているような空虚な部屋から離れないのではなく、そもそもこの部屋以外に帰る場所がないから部屋に居座り続けているのだとは思うまい。
「霧子は、ああ、霧子っていうのは俺の飼い主だった女なんですけど、なんか、変だったんですよね」
「変?」
「いやまあ、この不景気の時代に穀潰しの男を飼おうなんて女、ああ、まあ男もいたんですけど、そういうやつはだいたい変なんですけど。でも、わりとそういう変なやつもみんな考えてることは同じなんですよ。ヒモ飼って、甘やかしてもらって、自分の承認欲求満たしたい、みたいな。だいたいみんな親とか元カレとかがろくでもなくて、だからどうしようもなくさみしくて、それで俺みたいなカスにハマっちゃう」
今までの飼い主だった女のことを思い浮かべてみる。中には金を持て余しているから趣味で、なんていうのもいなかったわけではないけれど、だいたいはさみしい女、あるいは男だった。金を渡せば自分に都合の良い言葉を吐いてくれる男に縋って、こんなやつも生きてるな、なんて薄っぺらい安心を得る、バカなやつら。でもだんだん苦しくなったり、許せなくなったり、餌をあげなくても自分に優しくしてくれる善良な人間と出会ったりで、俺の首輪を鋏で切る。それをとくべつ悲しいだとかさみしいだとか思ったことはない。まあしょうがないかな、と思って、数日間のホームレス生活ののち、また新しい飼い主を見つけるだけ。もう名前も思い出せないやつらが大半だけれど、どこかで幸せにやっていればいいな、と思う。バカ犬にだって、飼ってもらったことに対する感謝くらいはあるのだ。
「だけど霧子は違った」
そう口にしてから、少し息を吐く。後部座席に座ってしまったせいで運転手の顔は見えないが、そのまっすぐに伸びた背筋はなんとなく霧子を想起させた。
「なんかクラスにひとり、めちゃくちゃ真面目なやつっているじゃないですか。先生が宿題提出するの忘れてて、よっしゃこのままやり過ごそうぜみたいな空気にクラスみんながなってる中で、わざわざ先生に宿題の話する、みたいな、空気の読めないやつ」
「正しいことをしてると思いますけど」
「はは、霧子みたいなこと言うんすね」
運転手からの返事はなかった。気を悪くしたのかもしれないけれど、俺には関係ないことだ。この車が目的地にたどり着いたら、俺とこの女は二度と会うことはないのだから。
たとえば愛玩用の犬が待て、や、お手、をできなかったとして、それを本気で叱る飼い主はいないだろう。なぜならその犬に求められているのは仕事に疲れた飼い主を癒すという役目だけであって、それは存在さえあればどうにかなるものだから、そこに躾は必要ない。ヒモというのは愛玩用の人間だから、俺もそういうふうに生きてきた。霧子に出会うまでは。
そういうのは良くないと思う、と霧子は言った。きみは人間だから、ちゃんと人間をやっていかなくちゃいけない、と。俺にそんなことを言ったのは霧子だけで、その言葉の通り、霧子は俺に人間をやらせようとした。
「皿」
「はい?」
「皿、洗えって言うんですよ。あと服干せとか、掃除機かけろとか。そういう、子どもにさせる手伝いみたいなの。しらーっとした顔で」
「はあ」
「ヒモにそういうことを求めるやつってあんまりいなくて。あいつらは自分がいなきゃなんもできない俺が好きで、そこに自分の存在意義を見出してるから。だから、そういうことを口うるさく言ってくるのって霧子が初めてだったんですよね」
「嫌だったんですか?」
ためらいのないその言葉に、思わず苦笑する。普通なんかこう、もっと言いようがあるだろ。
「そりゃあまあ、嫌でしたよ。俺は金もらってだらだら生活することしかしたくなかったし」
初めはもう最悪だった。俺は金をもらって悠々自適に生活したいだけなのに、やれ掃除だやれ洗濯だ、ヒモにそういうことを求めるほうが間違っているのに、霧子はしつこく俺に手伝いをさせ続けた。何度出ていこうと思ったかわからないし、実際昔の女のところに行ったことも一度や二度じゃない。なのになぜか、気づけば霧子の家に戻っていた。日当たりのいいアパートの三階。春先に窓を開けると桜の花びらが舞い込んできたあの部屋。今はがらんどうで、そのくせ部屋のどこにいても霧子の、清潔な石鹸みたいな匂いのする部屋。
でも長く居たんですよね、と運転手は言った。三年を長いというか短いというかは人によるだろうけれど、確かに俺にとっては最長記録だった。
「……本が、あったんすよ、霧子の部屋に」
霧子の部屋の本棚を思い出す。霧子の両親が引き取ってしまったから、今はもうない。小説が多かったけれど、漫画や雑誌もそれなりにあった。自由に読んでいい、と霧子は言った。感想が聞きたい、とも。
「本とか、ろくに読んだことなかったけど、案外悪くなくて。でも霧子の家から出て行ったら、続き読めなくなるから」
「だから暮らしてた?」
肯定の意を込めて頷こうとして、少し考える。確かに本は面白かったし、続きを読むために霧子の家に帰っていた日もあった。だけど、だけど本当は。
考えることから逃げるように視線を窓の外へ向けると、車の窓ガラスにぷつぷつと雨粒が張り付いていた。ああ、やばい。洗濯物、取り囲んできたっけ。霧子に怒られる。取り囲んでおいてよ、って、あの心地の良い冷たさを伴った目で。
「あ」
声が漏れた。ああ、そうだ。霧子はもう。
霧子と一緒に過ごした最後の夜も雨が降っていた。夕飯は冷やし中華で、食べ終わったらベランダで煙草でも吸おうと思っていたけれど雨が降っていたからやめて、代わりに昨日読んだ本の感想を霧子に話した。それ映画になってるよ、と霧子が淡々と言っていた。車にはねられた霧子は、右手にレンタルビデオ屋の袋を持っていたらしい。
滑り落ちるように声が出た。なんか、初めてで。初めて? と運転手は繰り返した。
「そういう、家のこと、とか。感想、とか、そういう、ちゃんと人っぽいやつ」
「人じゃないんですか?」
「いやぁ、まあなんか、ペット? 飼い犬? みたいな感じだったんで。ずっと」
あはは、と乾いた笑い声が出た。運転手の女は無言のままハンドルを回した。樹海、が具体的にどの辺りにあるのかなんて知りやしないから樹海に、なんて言ってしまったけれど、そういえばこの女は迷いなく車を走らせ始めた。大丈夫なんだろうか、いろんな意味で。あとどれくらいかかります? と聞いてみても返事はなかった。別に死に場所なんてどこでもいいから、最悪たどり着けなくたっていいんだけど。
雨は次第に勢いを増して、窓ガラスを打つ音は強くなっていた。車は水を撥ねながら走っている。凹凸の少ない道を、一定の速度で。
「楽しかったですか」
運転手が静かな声で言った。
「はい?」
「その人と、一緒にいること」
楽しかったですか。運転手がもう一度、そう聞く。冬の朝みたいな、静かな声。こんなどうしようもないやつを、ちゃんとひとりの人間として扱っていた、唯一の女の声だった。
葬式のことを思う。数人の友人と家族だけが集った、霧子の葬式。皿の効率的な洗い方、綺麗な服の畳み方、求人情報、おもしろい映画。そういう、霧子が教えてくれたたくさんのことの中に、葬式のマナーはなかった。霧子が死んだあと、どうすればいいのかも。
「なあ」
震える声で呟く。うん、と運転手が、霧子が言う。
「教えてくれよ」
「口座の番号?」
「バカ」
霧子は少し笑って、冗談、と呟いた。ルームミラーには、最後に見たときと変わらない霧子の目元が映っていた。いってきます、と霧子が玄関先で言って、いってらっしゃい、と俺が返した朝。ただいまはなくて、代わりに警察からの電話があった。霧子が車にはねられて死んだ、ということを伝える声は静かで淡白で、でも同じ淡白でも霧子のそれとはまったく違っていた。
楽しかったですか、と霧子は聞いた。俺よりもずっと頭いいくせに、そんなわかりきった質問すんなよ。楽しかったに決まってる。怒られてばっかだったけど、それでも。楽しかったよ。お前が俺を人間にしてくれたあの時間が、俺は。
霧子。
「霧子」
「うん」
「はねられんなよ」
「ごめん」
映画のこと考えてて、と霧子が肩をすくめる。そういう仕草の、声の、言葉のひとつひとつがやっぱりどうしたって霧子で、けれどそこにいるのが霧子であればあるほど霧子の死は輪郭を持って俺に近づいてきた。
タクシーは急に止まって、霧子は車から降りた。つられて、のろのろと車から降りる。子どもみたいだ、と思う。親のあとを、わけもわからずついていく子ども。そこは樹海でもなんでもない、ありふれた街の駐車場だった。アスファルトが雨に濡れていて、それがなぜか苦しかった。
さっきまで着ていたはずのタクシー会社の制服はなぜかすっかり姿を変えて、霧子が家でよく着ていた部屋着になっていた。白いスリップ。それを着て、ソファの上でお酒を飲みながら本のページをめくっている霧子の横で、適当な本を読んでいる時間が好きだった。生きている、と思った。
霧子は、雨に濡れた車にためらいもせず寄りかかりながらひっそり、四つの数字を言った。覚えのない数字だった。
「なにそれ」
「口座の暗証番号。あんまり入ってないけど、まあ生活はできるかなってくらいには」
「そんなの、知ったって」
「資金源がなくなっちゃったから、じゃなかったっけ?」
霧子がいたずらっぽく笑う。そういえばそんなことも言った気がする。違う、と呟く声が震えた。わけもわからず涙が出た。
「違うの?」
「違う」
「じゃあ、本当は?」
霧子の目がじっと俺を見つめている。霧子はいつだって俺の目を見て話をした。
「しんどい」
嗚咽混じりに言う。一度言ってしまえば、口からは驚くほどたくさんの言葉が出てきた。しんどい、さみしい。苦しい。なんで死んだんだよ。どうして一人にすんだよ。俺一人だったらなんもできないのに。霧子がいなかったら、どうしようもないバカ犬でしかなかったのに。なあ、霧子。霧子。きりこ。
声をあげて、子どもみたいにみっともなく泣きわめく俺に、霧子はそっと触れた。触れた、のだと思う。そこには体温も手のひらの感覚もなくて、それが悲しくてまた泣いた。
「大丈夫だよ」
霧子が言った。優しい声だった。
「なにが」
「きみが」
「大丈夫じゃない、ぜんぜん」
「大丈夫」
私がいなくても生きていけるよ、と霧子は言った。そんなことを、そんなにさみしそうな顔で言わないでほしかった。ずっとそばにいるよ、とか、ひとりじゃだめそうだもんね、とか、そういうことを言ってほしかった。そしたら俺は、やっぱそうだよな、なんて笑って、霧子のところに行くのに。
でも霧子は、そうは言わなかった。大丈夫、と霧子がまた言う。小さな子どもに言い聞かせるみたいな声で。大丈夫、きみはもう、ちゃんと人間をやっていけてる。
「でも霧子がいない」
「いるよ」
「どこに」
「どこにでも」
雨はいつの間にか止んでいて、霧子の声だけが駐車場に響いていた。雨に濡れたアスファルトに触れる霧子の裸足の足の、まるい爪が目に入った。霧子は足の爪をまめに切り揃えていた。
「きみがさ、洗濯物を干したり、掃除をしたり、映画を見たり本を読んだりしてる、その中の、どこにでも」
いるよ。霧子はそう微笑んで、また、大丈夫、と言った。
「ね、だから泣かないでよ」
「……むり」
「無理じゃない」
霧子が苦笑しながら、指先で俺の涙を拭う。一瞬、ほんの一瞬だけど、そこには霧子の温度があった気がした。冷たくて心地よい、霧子だけのあの温度。
「だから、ちゃんとやってね。約束」
淡い光を纏った小指が目の前に突き出される。指切りげんまん、とかいう、子どもじみた儀式。俺がちゃんと日々をやるなら、霧子はずっとそこにいてくれる。そういう約束事を、断れるはずがなかった。
小指を伸ばす。霧子は満足そうに笑って小指を絡めると、小さな声でがんばれ、と言った。好きでも愛してるでもないところが霧子らしいと思ったし、俺たちだと思った。がんばる、と鼻声で返す。それから一瞬まばたきをして、目を開けると霧子も、タクシーも消えていた。
泣きすぎてだるさの篭る頭の片隅で、金を下ろそう、と思った。霧子が残していたらしい金を。今さっきまで自分の身に起きていた非現実的な出来事への帰結としてはあまりにも現実的で生々しいけれど、生活とはいつだってそういうものなのだからしょうがない。金を下ろして、切れかけの電球を買おう。飯を買おう。カップラーメンじゃなくて、ちゃんとしたやつ。それから、レンタルビデオ屋に行こう。霧子が言っていた映画を借りに。そういう日々を、明日も、明後日も、ずっと。
霧子はもういないけれど、霧子がくれた日々は変わらず、そこにいてくれるのだから。
これでいいんだよな。さっきまで霧子が立っていた、今は誰の姿も映していない水たまりに向かってそう呟く。返事はなかった。けれど水たまりが一瞬だけ、上にいる誰かが足を踏み出したように揺れて、俺の頬に心地のいい冷たさを孕んだ風が吹いて、それでもう十分だった。
小説「とぅ・びー・こんてにゅーど」
投稿者:
タグ: