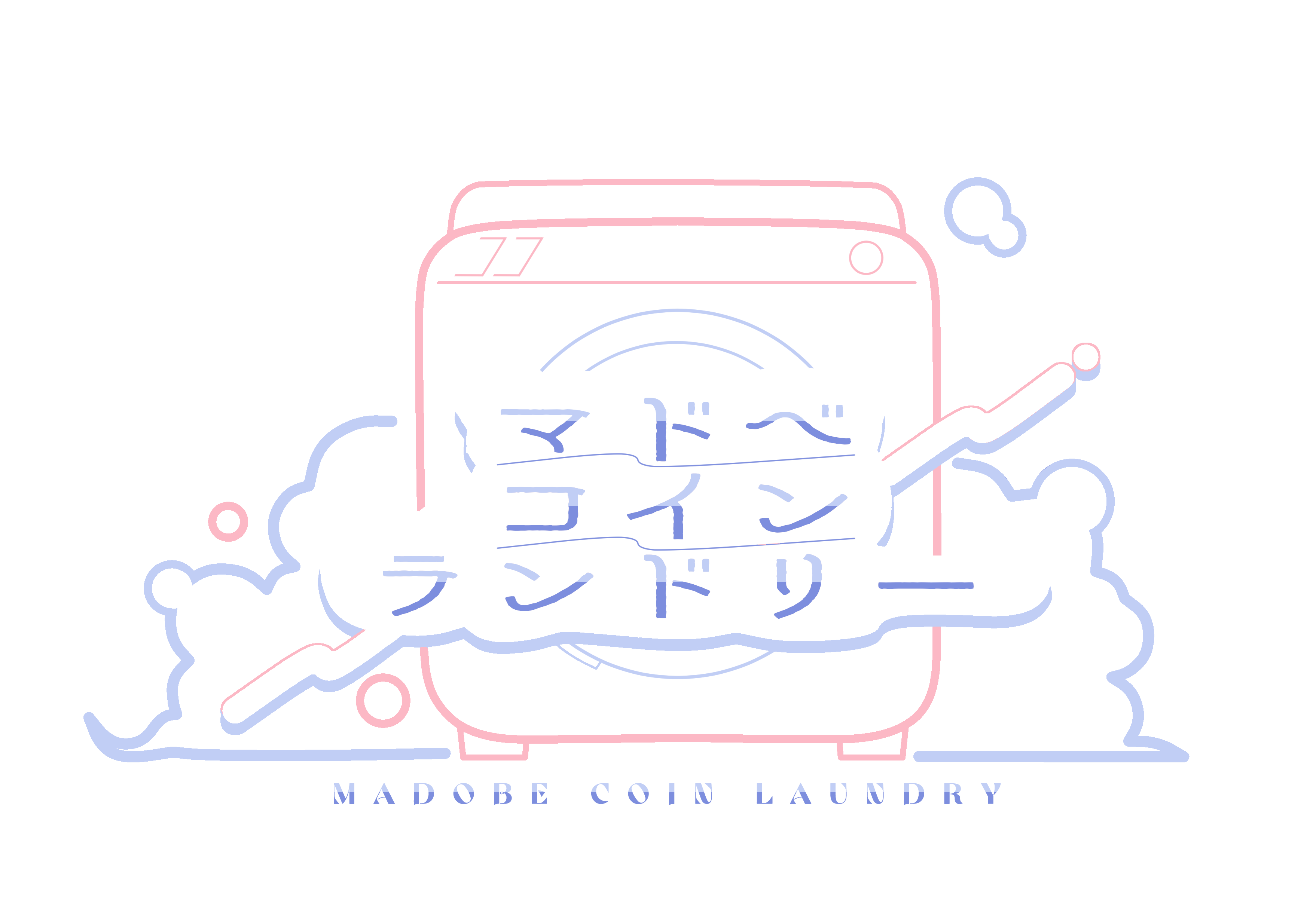いなくなっていてほしい、と思う。それと同じくらい、いてほしい、とも思う。矛盾を鼻で笑いながらドアを開けると、すぐに、おかえり、と声がした。小さなため息が漏れる。
「……ただいま」
そう返事をしてから、素直に返事をした自分に嫌気がさした。無視を決め込んでやればよかった。これじゃあまるで、この男がこの家に居座っていることを受け入れているみたいだ。
俺が部屋に帰ってきてもなお、兄は俺のベッドから動こうとはしなかった。寝転がってスマホを眺めて、たまにぼうっと天井を見上げている。唐突に俺の家を訪ねてきてから一週間、兄はずっとこうだった。おかげで俺は来客用の薄い布団で寝る羽目になっている。いい加減、腰が痛い。
「飯食ってきたから」
「ん」
「兄さんは。なんか食ったの」
「ん」
返事になっていない。とはいえ聞き返す気も起きなかったし、まともな返事が返ってくる気もしなかった。そもそも、俺が兄の食事を気にする義理なんてどこにもない。そんなことを言ったら、家に泊めてやる義理だってないのだが。
兄が家を出て消息を絶ったのは、今から六年ほど前のことだった。元々外泊が多く、ろくに帰ってきやしない人間だったが、いつのまにか一切顔を見なくなっていた。あんな出来損ないはうちにはいなかった、と父は言い捨てた。母はなにも言わなかった。俺がなにを言ったかは、覚えていない。
シャワーを浴びるために浴室に入ると、風呂場に赤い髪の毛が落ちていた。明らかに兄のものだった。一日中ベッドにいるものだとばかり思っていたが、どうやらシャワーは浴びているらしい。兄の赤い髪の毛は、最初こそ面食らったものの、一週間で見慣れてしまった。
しばらくすると、部屋のほうから声がした。あー、もしもし。兄が気だるげにそう言っているのがわかった。なんとなく、シャワーに伸ばしていた手を下ろしてしまう。
「んー、ああ、そ。いまは、弟の家」
力の抜けた言い方からして、相手は友人なのだろう。もしくは恋人だ。いるのかは知らないが。改めて、自分は兄のことをなにも知らないのだと思う。兄が今までどこにいてなにをしていたのかも、なぜ俺のところに来たのかも、俺はなにも知らない。この一週間、聞こうと思ったことがないわけではなかった。家に泊めるんだったら、聞いたほうがいいに決まっている。
けれど、俺はなにも言えなかった。兄の、鬱屈とした横顔を見るたびに、俺のなかに少しずつ、言えない言葉が溜まっていった。
「ああ、うん、そう。例のね、優秀な弟」
俺とは違って、と兄が苦笑する声が、聞こえてきた。たまらなくて、シャワーのハンドルをひねる。吐き出された水は思ったより冷たかったけれど、温度なんてどうだったよかった。風呂場に落ちていた赤い髪の毛が、水の勢いにつられて排水溝に吸い込まれていく。
「あー、洋平?」
その声ともに、浴室のドアが数回ノックされる。飲みにいってくるわ、と兄は少し声を張り上げて言った。飲みの誘いの電話だったらしい。勝手にすれば、と吐き捨てる。実際、ここは兄の家ではないのだから出かけるのも出ていくのも勝手にすればいいことには違いない。それなのに、勝手にすれば、と口にした瞬間、心臓をざらりとしたものが這ったような気がした。
やがて、がちゃりと玄関が開く音と、いってきます、という兄貴の声が聞こえてきた。いってらっしゃい、と小さな声で返事をする。なんだか、ひどく疲れた。
部屋に戻ると、母親からのメッセージが届いていた。仕事、いつから夏休み? 戻ってくる時期がわかったら教えてね。その二文に、うさぎのスタンプが添えられている。戻らないという選択が自然に消去されているような文章だ。もちろん、母親は無意識なのだろう。母親には、兄が来ていることは伝えていない。
優秀な弟、という兄の言葉を頭の中で反芻する。昔は逆だった。優秀な兄と、普通の弟。兄が受験に失敗したことで、俺たちは普通の兄と普通の弟になり、そして、俺が受験に成功したことで俺たちの立場は完全に入れ替わった。普通の兄と、優秀な弟。
いなくなっていてほしい、と思う。それと同じくらい、いてほしい、とも思う。そういう矛盾が俺の中に存在している理由を、俺は、本当は知っていた。俺が兄に、なにも聞けないでいる理由も。
誰もいないベッドを見るのは一週間ぶりだった。今ここで寝てしまえば、腰の痛みが多少改善されるのはわかっている。それでも俺の体は勝手に、来客用の薄い布団へと向かっていた。