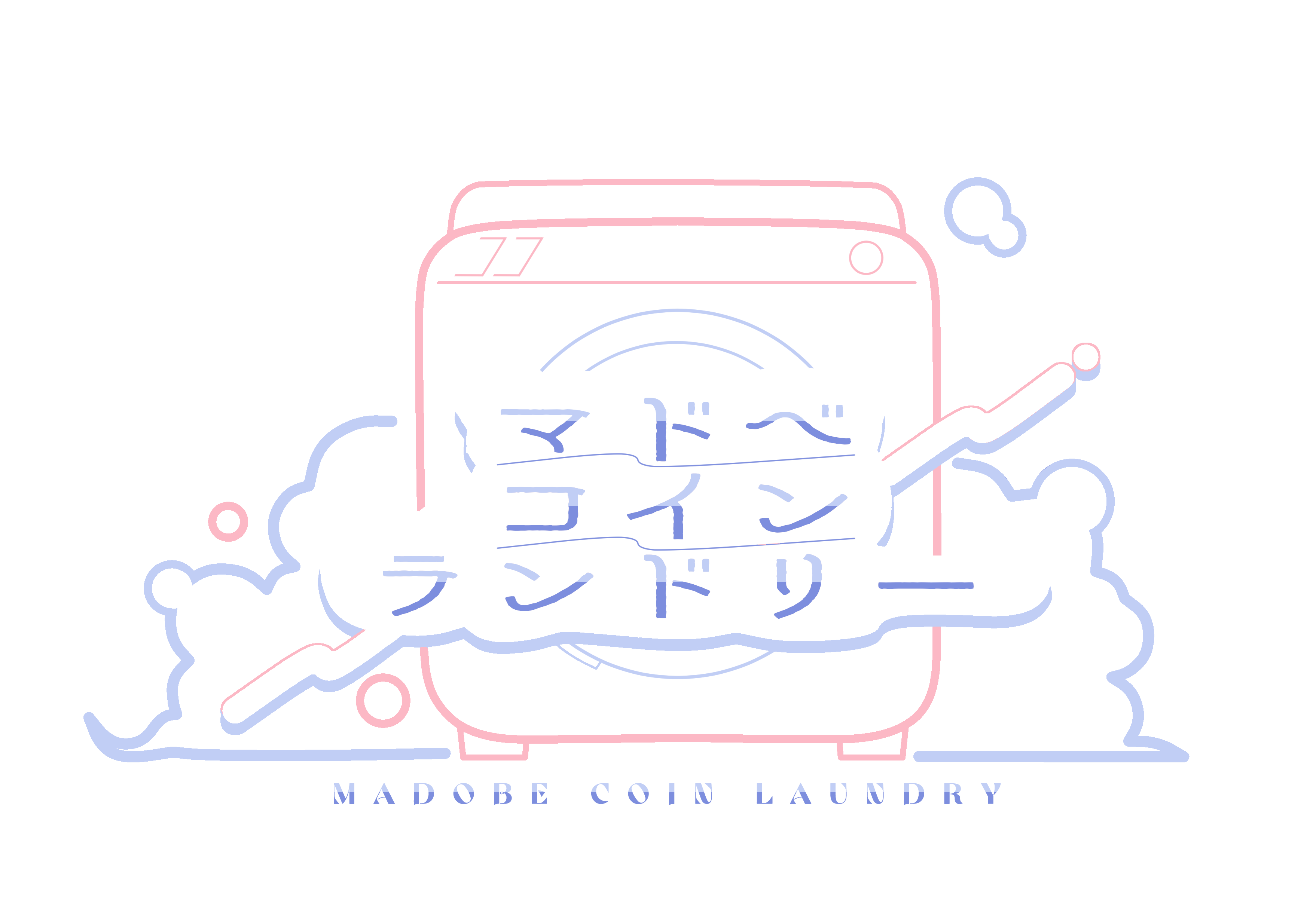幼馴染が、ロボットに乗るらしい。ロボット。ロボット? 言っている意味がよくわからなくて、頭の動きが止まる。意味わかんないよな、と悠人が苦笑した。うん、意味わかんねえ、と呆けた声で返す。DAMチャンネルをご覧の皆さまこんにちはぁ。知らないアーティストが挨拶をする声が、やたらと鮮明に聞こえた。
「え、旬。これどうやって音下げるの」
「その、ダイヤルのところ。ああ、それはマイク音量」
悠人が不慣れな手つきでダイヤルを回す。やがてスピーカーから聞こえていた音楽は、内緒話をするくらいの音量になった。それに負けないくらいのひそやかな声で、悠人が言う。なんか、宇宙人が攻めてきてる? みたいで。
「はぁ?」
「マジなんだって。宇宙人が攻めてきてるから、おれにロボットに乗って戦ってほしいらしくて」
「おまえそれ、騙されてるだろ。財布とか取られてないか」
「おれも騙されてるって思ったんだけどさぁ」
これ見て、と悠人が見せてきたスマホの画面には、俺でも知っているような有名人が映っていた。この国の総理大臣だった。総理大臣と、悠人が映っていた。二人ともピースサインをしている。悠人はともかく、総理大臣がピースをしているのはなんなんだ。っていうか、そもそも、なんなんだよ、これは。
「信じた?」
「信じたもなにも、なんだよ、これ」
「総理。おれが説明受けた場所にいてさ、写真撮ってもらった。意外とノリ良くて気さくなおじさんだったよ」
なんの冗談かと思ったが、悠人の顔は真剣だった。自分の頬を引っ張ってみるけれど、しっかりと痛い。悪い夢、じゃない、らしい。夢じゃないよ、と悠人が笑う。
「……マジで?」
「うん。ロボットの本物も見せてもらった。なんか思ったより黒くて地味だったよ、そのうちニュースとかになると思うけど」
それから悠人は淡々と、事の経緯について説明した。宇宙人が攻めてきていること。そいつらと戦うためのロボットに搭乗するパイロットに、悠人が選ばれたこと。おおむねさっき聞いたことの繰り返しだけど、まだにわかには信じがたい。けれど、悠人がそういう嘘をつく人間じゃないことも、俺はよく知っていた。なにより、悠人がどうでもいい嘘をつくために、この場所を選ぶとは思えなかった。アニメみたいだよな、とへらへらと笑う悠人の横顔をちらりと見る。暗い部屋の中でもはっきりわかるくらい、青白い顔。
「ロボットって、あれか。なんか、操縦席とかあるタイプ」
悠人が一瞬だけ、笑うのをやめる。ああ、やっぱり、と思う。俺の勘は、どうやら正しかったらしい。
「大丈夫なのか。おまえ、そういうのだめだろ。窓がないところとか」
閉所恐怖症。悠人の口からその言葉を初めて聞いたのは、小学五年生のときだった。ヘイショキョーフショーなんだ、おれ。窓がないところとか、暗くて狭いところに閉じ込められると、頭がまっしろになって、吐きそうになる。そう言ってげぇ、とゲロを吐くジェスチャーをした悠人の顔は、笑っているのに苦しそうだった。
母親がさぁ、ヒスると、おれのこと押し入れに閉じ込めんの。自分で産んだくせに、顔も見たくないって。悠人が、答え合わせのようにひっそりとそのことを教えてくれたのは、それから三年後のことだった。そのときもやっぱり、悠人は笑っていた。今と同じに。
「まだだめなんだな、これが」
「は? じゃあ」
「だからとりあえず、カラオケで練習ってことで」
そう言われて、ようやく悠人がカラオケを選んだことに納得がいった。カラオケなんていう閉塞感の塊みたいな場所は、本来であれば悠人のもっとも苦手とする場所だ。実際、俺は今まで悠人とカラオケに来たことはないし、今日だって誘われたときは耳を疑った。いいから、と悠人がめずらしく強引に押してくるものだからなにかしら理由はあるんだろうと思っていたけれど、なるほど、練習。
「断ればいいだろ、閉所恐怖症なんで無理ですって」
「そういうわけにもいかないだろ」
悠人がデンモクを操作しながら苦笑いをする。ぴ、ぴ、ぴ、とむかつくくらいに軽快な音が部屋に響く。そういうわけってどういうわけだよ、と聞きたかったけれど、それを聞くのはちょっとガキっぽすぎる気がした。わかってる、俺に悠人を止める権利はない。この国を守るためにロボットに乗って戦う。男なら誰もが憧れるシチュエーションだし、それを実際に成し遂げるのならこんなにも立派なこともない。それでも、心臓はざわついていた。
悠人への言葉を考えているうちに、カラオケの機械から音楽が流れ始めた。いつの間にか音量を上げたらしく、何度か聞いたことがあるポップスが部屋中に響き始める。歌える? 悠人がそう言って、俺にマイクを向けた。わけがわからなかった。
「いちおう、歌えるけど」
「じゃあ歌ってよ」
知っている曲だから、歌えるには歌える。ただ今は、楽しくカラオケ、なんていう気分では到底なかった。っていうか歌わせるなよ、こんな話の後で。困惑と、それから若干の怒りを滲ませて悠人を睨む。だけど悠人は間奏の二文字が映し出された画面を見つめたまま、俺のほうを向きはしなかった。
「旬さ」
悠人が画面を見つめたままで言う。もう間奏の二文字は消えて、誰も歌わない歌詞が流れては消えていっていた。
「なんだよ」
「あんま上手くないよな、歌。小学生のときも、音楽のテストとか何回も歌わされてたし」
うるせぇ、と悠人の脛を軽く蹴る。確かに、俺の歌は上手くはない、というか普通に下手だ。ただ、それを今まさに、俺に歌を歌わせようとしているやつに言われるのはむかついた。知ってんなら歌わせんなよ、とぼやく。うん、と悠人は頷いて、それから、でも、と言葉を続けた。でも、だから、思い出したら笑っちゃうかなって。
しばらく、言葉の意味を考える。やがて、ああ、とため息のような声が無意識に漏れた。ああ、そういうこと、と呟く。そういうこと、と悠人は澄ました顔で言った。そういうことなら、仕方あるまい。悠人の手からマイクを奪い取って、一回、大きく息を吐く。マイクに呼吸の音が乗って、部屋中に濁った音が響く。画面に表示されているのは一番のサビだった。しょうがないから、でかい声で歌ってやる。ほとんどやけくそだった。むりやりサビから歌ったせいで声は裏返っているし、そもそもうろ覚えなせいでところどころリズムがおかしい。音程バーはさっきからひとつも合っていない。今の俺は、さぞ滑稽なことだろう。それこそ、苦い記憶をかき消してしまうくらいには。
へたくそ、と悠人がげらげら笑いながら言った。歌わせておきながら、良いご身分だ。腹が立って、声にはさらに勢いが乗った。どんどんテンポが崩れていく。それでも俺は歌うのをやめなかった。操縦席で、孤独に息をひそめている幼馴染のことを考えながら、俺はずっと、ばかみたいに歌った。