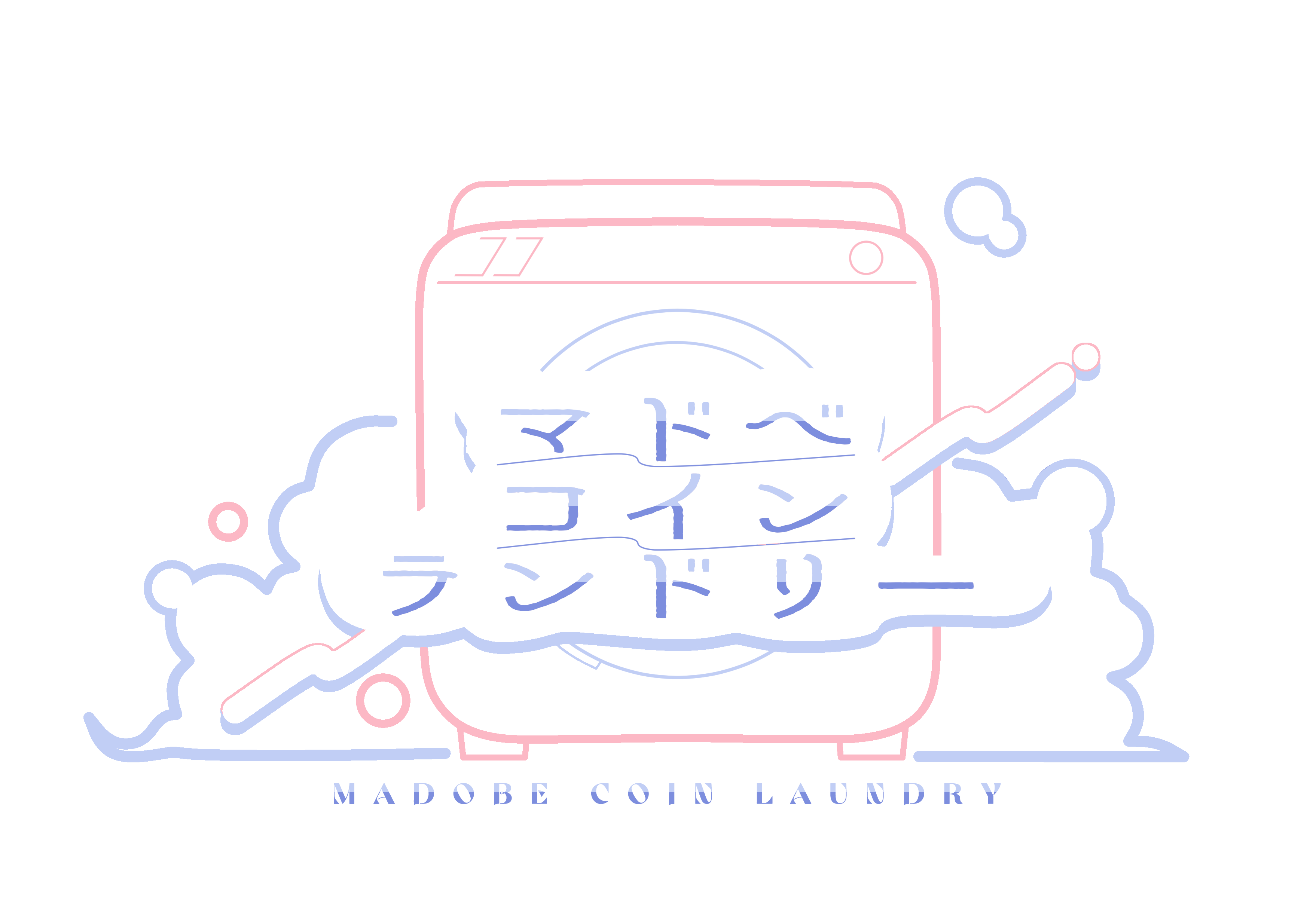昔々、ある王国に、ふしぎな悪魔がいました。悪魔といっても、人を呪ったり、傷つけたりするいきものではありません。それは、人間の感情を食べる悪魔でした。よろこび、かなしみ、いかり……人間に発生した感情は、目に見えていないだけで、実はふわふわとあたりを漂っています。悪魔はそれを食べるのです。むしゃむしゃ、もぐもぐと。
悪魔に感情を食べられた人は、やがてそれを忘れていきます。食べられてしまった感情は、けれど、完全になくなるわけではありません。よく食べ、よく働き、よく眠れば、また感情は生まれます。それをまた、悪魔は食べるのです。むしゃむしゃ、もぐもぐ。
かなしみやくるしみが食べられるだけなら、それはいいことかもしれません。しかし、悪魔は健啖家でした。よろこびもたのしみも、しあわせだって食べたいのです。
国王さまは、この悪魔にほとほと困りはてていました。なんでって、感情を食べられてしまった国民がみーんな、無気力になってしまうからです。しばらくすればまた元通りになるとはいっても、悪魔が食事を続けるかぎりはきりがありません。そこで国王さまは、悪魔とひとつの契約を交わしました。
それは、国王さまの一族からしか、感情を食べないということです。国王さまは、王さまという人間に感情はいらないと考えていました。国を守り、国を導く人間に、感情なんて邪魔なだけ。それが国王さまの考えでした。なので、感情を食べる悪魔というのは、国王さまにとってはとても都合がよかったのです。
もちろん、悪魔は嫌がりました。ぼくはたくさんの人の感情を食べたいんだ! そう怒った悪魔でしたが、ある少年を見て、悪魔の気は変わりました。悪魔の目を奪った、うつくしい少年。それは、この国の王子さまでした。
王子さまと言っても、その少年は妾の子、不義の子でした。ですから、この国の本当の跡取りにはなれっこありません。けれど悪魔にとっては、そんなことはどうだっていいことでした。
悪魔がくらくら見惚れてしまったのは、彼のまわりに漂っている、暗く重たい感情でした。この世のすべてが、憎くて憎くてたまらない。よろこびやしあわせなんて、この魅力的な感情の前では霞んでしまいます。ああ、なんてうまそうな感情! 悪魔は王子さまに、人間でいうところの一目ぼれをしてしまったのです。悪魔はたまらず、国王さまと契約を交わし、王子さまの感情をおいしくいただきました。
王子さまの感情は、食べても食べても溢れてきました。ああ、なんでかわいそうな子ども、と、悪魔は彼の感情を貪りながら思いました。どれだけ感情を食べられても、次から次へとうらみや、くるしみや、いたみが湧いてくる。彼の置かれている環境がそうさせているのか、それとも持って生まれた気質なのか。悪魔にはわかりませんでした。
何年も何年も、悪魔は王子さまの感情を食べました。王子さまは悪魔に、きたなく、よどんだ感情を食べさせました。するとどうでしょう、だんだん、王子さまのなかに、またべつの感情が生まれてきたのです。
最初はメイドでした。冷遇されている王子さまに、ずっと優しく寄り添い続けてきたメイドです。王子さまはある日ふと、彼女がずっと自分の味方であったことに気づきました。世界にいるのは、自分の敵だけじゃない。そう気がついた王子さまは、その日はじめて、人のために花を買いに行きました。そのとき王子さまのまわりに浮かんでいた感情を、悪魔はいつも通り食べました。むしゃむしゃ、もぐもぐと。その感情は甘く、美味でしたが、悪魔はなんとなく、物足りない心地でいました。
次は弟でした。不義の子である王子さまと、王子さまの弟は、血がつながっていません。けれど弟は、ほんとうは、王子さまとずっと仲良くなりたいと思っていたのです。あるとき王子さまは、弟が自分の書棚の前に立っているのを見つけました。今までの王子さまだったら、弟を追い払っていたでしょう。けれどその日、王子さまは生まれて初めて、弟に本を読み聞かせてあげました。なぜそうしたのか、王子さまは自分でもよくわかっていませんでした。不慣れな声で絵本を読み聞かせる王子さまのまわりに浮かんだ感情を、悪魔はまた、いつも通り食べました。むしゃむしゃ、もぐもぐと。その感情はおだやかで、美味でしたが、悪魔はやっぱりなんとなく、面白くない心地でいました。
そういうことが、しばらく続きました。そしてあるとき、悪魔は気づいたのです。今の王子さまが、自分が一目ぼれした王子さまではないことに。悪魔が一目ぼれした王子さまが持っていた、ぎらぎらとした負の感情は、いつのまにか、すっかり薄れていました。
そのことに気づいた悪魔は、深く深く絶望しました。ああ、どうして。どうして王子は、こんなふうになってしまったんだろう! ぼくが感情を食べてしまったから? ぼくはただ、ぼくが食べたいものを食べ続けたかっただけなのに!
嘆き悲しんだ末に、悪魔はひとつの考えを思いつきました。きっと王子はもう二度と、ぼくの愛した王子には戻らない。じゃあいっそ、彼を感情ごとぜんぶ、食べ尽くしてしまえばいいんじゃないか? 体をぜんぶ食べてしまえば、もしかしたら、ぼくの愛した王子だって、ほんのすこしは残っているかもしれない。ふだん、悪魔は人を食べることはしません。けれど、人を食べられないわけではないのです。
王子さまを食べてしまおう。残さずぜんぶ、自分のものにしてしまおう。そう決めた悪魔はさっそく、王子さまの眠る部屋を訪れました。王子さまはベッドで眠っていました。悪魔が近づいても、起きる気配はありません。枕に沈んだ横顔は、もうすっかり大人のものでした。出会ったころは、あんなに子どもだったのに。
すやすや、王子さまは眠っています。悪魔はその手をそっと取り、口元に運びました。いただきます、と悪魔が小さくつぶやきます。すると王子さまの口から、ぽつり、言葉がこぼれました。それは彼の弟の名前でした。悪魔は知らないことでしたが、ここのところ王子さまは、弟と一緒に昼寝をすることがありました。王子さまは弟と悪魔を勘違いしていたのです。
幸福そうな寝言、幸福そうな寝顔。悪魔はしばらく王子を見つめて、やがて、その手を降ろしました。
食べるなんて、本当は、できるわけがありませんでした。王子さまをまるごと食べてしまうには、悪魔はあまりにも、王子さまと一緒にいすぎてしまったのです。悪魔はとうに王子さまを愛していたのでした。王子さまの、純粋な幸福を願ってしまうほどには。
悪魔は王子さまの手を離し、そっと部屋を出ました。王子さまの寝顔のまわりにはふわふわとおいしそうな感情がたくさん浮かんでいましたが、悪魔はもう、それを食べる気にはなれませんでした。