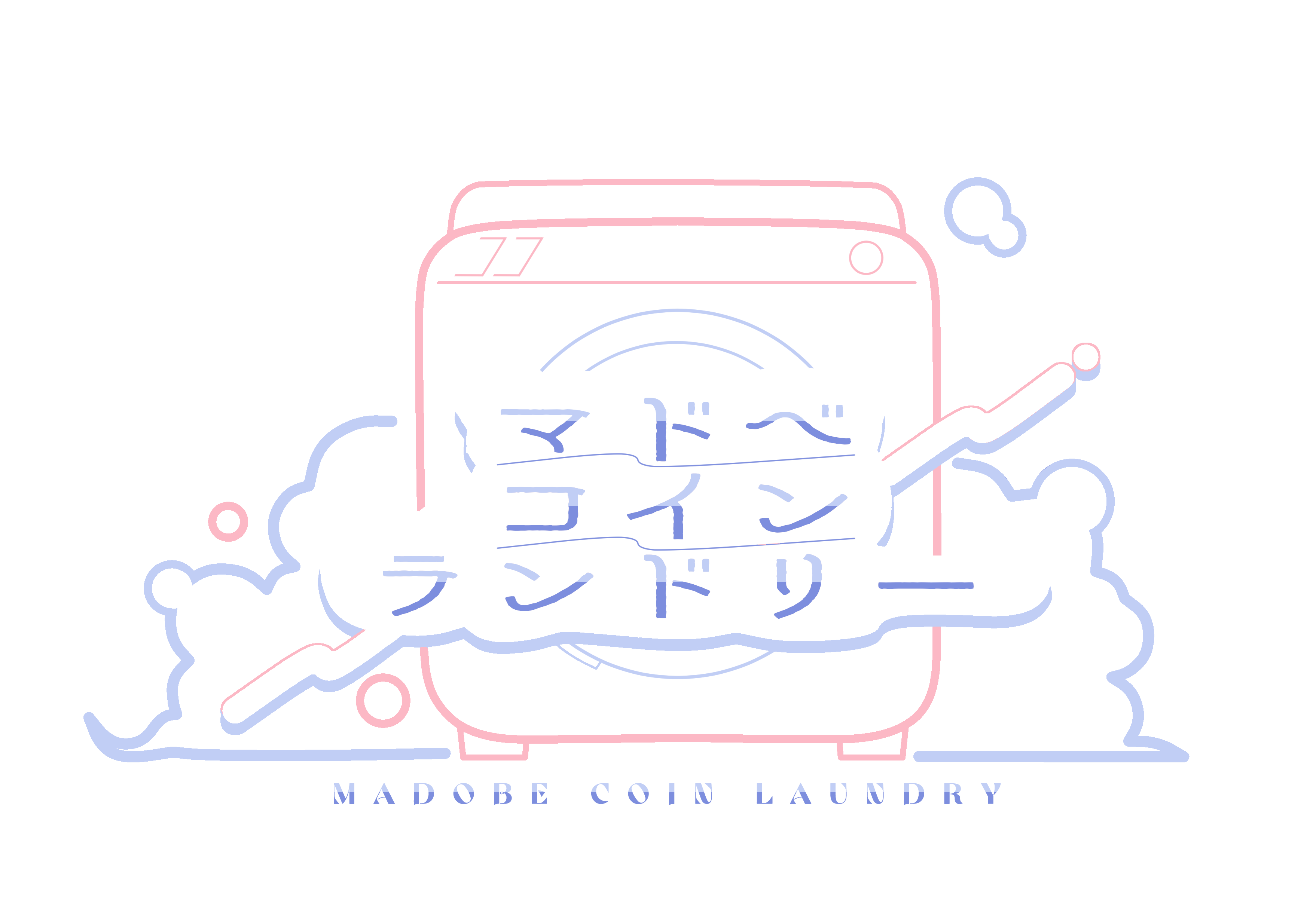適切
大丈夫? とか、なんかあった? とか、朝からそういうことしか聞かれなくて嫌になる。心配は善だという世間一般の価値観が間違っているとは思わないけれど、こうも同じことしか聞かれないのはうんざりだ。
とはいえ、窓ガラスに映る自分を目にすると揃いも揃ってみんなが同じことを言う気持ちもやっぱり理解はできる。あらためて、すごい色だ。いや、金色というのはべつに、髪の色としては珍しくないのかもしれない。外国人だとありふれているし、日本だって、街を少し歩けば見つけられるだろう。
だからこのすごい色、というのは、ぼくにとってのすごい色、というだけにすぎない。窓の隙間から入り込んだ風が、わずかにぼくの髪を揺らす。視界に、細い金色の髪が映る。髪の毛全体で見るとたしかにそれは金色に見えるのだけれど、いま、一本いっぽんがばらばらに揺れているのを見ていると、なんだかそれは透けているように見えた。ぼくみたいだな、と思う。今朝のリビングでのぼくは、たしかに、透けていたと思う。
弟のとったメダルとぼくの髪の毛は、同じ金であるはずなのに、どうにも両親の中では別物らしい。まあそんなことは、ずっと前からわかっていたんだけどさ、と小さく呟いてみたりしてみる。いまさら髪を染めたくらいで両親がぼくに興味を持つなんて、そんな都合のいいことは思っていなかったけれど、まさか説教すらないとは思わなかった。金髪が反抗の象徴である時代は、どうやらとっくのとうに終わっていたらしい。
「えっ、うわ、金じゃん」
唐突に、頭上から声が降ってくる。顔を上げると、隣の席の深山がそこにいた。いつも遅刻ばかりのくせに、今日は始業ベルよりも早い登校だ。めずらしいなこともあるものだ、と思う。もっとも、深山からしたら、いきなり隣の席の真面目野郎が金髪になっていることのほうがめずらしいんだろうが。目が、めずらしいものを見る目になっている。
深山は髪の毛を深い青に染めている。この色になったのは最近のことで、少し前までは明るい金色だった。今のぼくと同じような。いや、深山のほうがもっと色が淡かったかもしれない。髪の毛の色を抜くことをブリーチと呼び、ブリーチの回数を重ねれば重ねるほど、色が薄くなり、髪は痛んでいく、と昨日の美容師は教えてくれた。寒色系は二回以上ブリーチしたほうがいいんですよねー、とも言っていた。美容師の説明を聞くたびに、今までの深山の髪色の変遷が意味を持っていく気がした。
深山の次の言葉を考えてみる。え、なに、どうしたん急に。なんかあった? あるいは、なにも言わないで席に座って、始業までの短い時間を居眠りに費やすか。前者だったら億劫だし、後者だと少し傷つくな、と思う。われながら、面倒なやつだ。
けれど深山の反応は、そのどちらでもなかった。
「いいじゃん、似合ってる」
うその匂いがまるでしない、からっとした声だった。っていうか、髪もちょっと切っただろ。それも似合ってる。深山が無邪気に笑って言う。確かに、髪も切った。美容師に勧められるがままに。似合っていると言われることも、髪を切ったことに気付かれることも、どちらもぼくの予想外のことで、動揺して言葉に詰まる。けれどほんとうは、そう言われるんじゃないかと心のどこかで思っていたような気もする。ううん、違うな。ぼくがそう言ってほしかっただけだ、たぶん。過剰な心配でも、無関心でもないそれが、ぼくはずっとほしかったのだ。
胸が、妙に熱かった。ありがとう、と少し口早に言う。深山はなぜ礼を言われたのかよくわかっていないような顔で、少し首を傾げて微笑んだ。