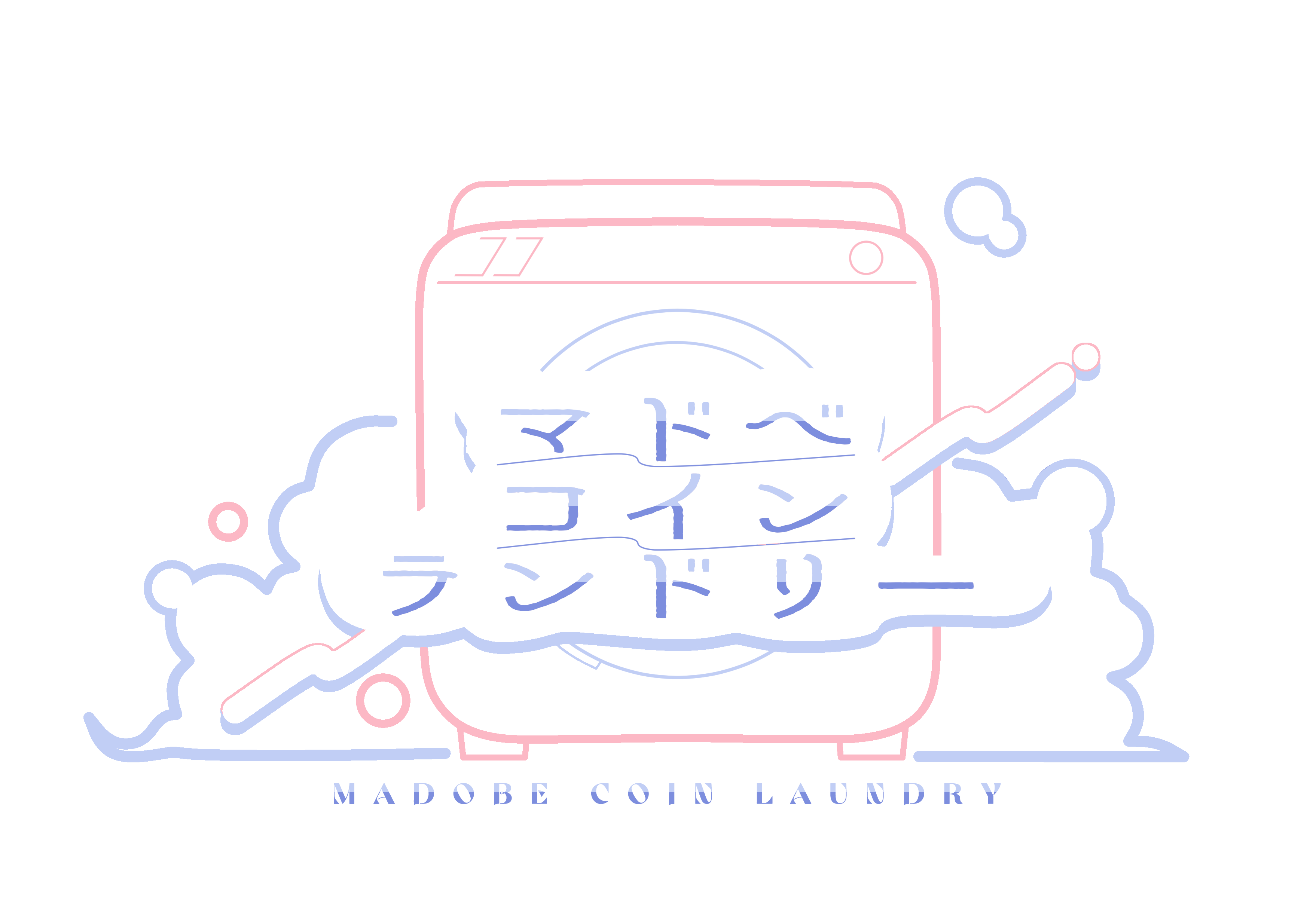ハロはおれをじいちゃんに似ていないというけれど、写真を見る限り、それは嘘だと思う。魚屋の松じいも畳屋の元じいも、おれの顔を見るたびに若いころのじいちゃんに似ているって言うし。ハロだけが、似てない、まったく似てない、と頑なにそれを否定する。
「でも似てると思うんだよなぁ」
「おい待て、なんだそれは」
「じいちゃんの昔の写真。この前家掃除してたら出てきた」
押入れの奥から出てきたアルバムの表紙には、今から約六十年近く前の西暦が書かれていた。つまり、そこに収められていた写真に写っているじいちゃんは、十代のじいちゃんということになる。そんでもって、じいちゃんの横で仏頂面をしながら写っている、このときのハロは。
「……ハロ、このときいくつ?」
「覚えているわけないだろ。四百歳は超えていたはずだが」
「はー、すご」
四百。何度聞いたって、くらくらするような年月だ。本当に見た目とか変わらないんだな、とおれが言うと、当たり前だ、とハロは不機嫌そうに鼻を鳴らした。
ハロは吸血鬼らしい。らしい、というのは血を吸っているところをおれが見たことがないからだ。ハロ曰く、子どもには見せられない、らしい。子どもって言ったって、おれだってもう十七歳なんだけど。でもまあ、四百年生きているハロからすれば、おれなんて赤ちゃんと変わらないんだろう。
改めて写真に映るじいちゃんと、ハロの家の窓ガラスに映る自分の顔を見比べてみる。自分で言うのもなんだけど、やっぱり似ていると思う。目の辺りがとくに。そんなおれの考えを見透かしたみたいに、ハロは、似てないからな、とぼやいた。
「弥太郎はもっといい男だった」
「おれだっていい男だけど?」
「どこが」
ハロが鼻で笑う。弥太郎というのはじいちゃんのことだ。自分のじいちゃんが名前で呼ばれているのは、なんだか不思議な感じがする。
ぱ、といきなり、手元から写真が奪われた。
「このときの写真か。懐かしいな」
「あ、ちょっと。奪うなよ」
だが断る、とハロが顔を顰める。本来ハロとじいちゃんの写真だからハロが持つのは当たり前なのかもしれないけれど、それにしたって自分勝手だ。
「なんのときの写真? それ」
「弥太郎がカメラを買ったときの写真だな。僕は映らなくていいと言ったんだが」
だからこんなに仏頂面なのか。いや、ハロはいつもこんな顔ではあるけれど。おれとも撮ってよ、となんとなく言ってみる。おれも、ハロとの写真がほしかった。
「嫌だ」
「ケチ」
「友達と撮りなさい」
「ハロだって友達だろ」
「同年代の」
おれは誰かとの写真じゃなくて、好きな人との写真がほしいんだけど。口には出さずに、そう思う。口に出さないのは、そう言ったところでハロに軽くあしらわれるのを知っているからだ。ハロはたぶん、おれがハロのことを好きなのをわかっている。わかったうえで、躱している。子どもの戯れだと思っているのだ。
はは、と口元を緩めて、ハロはじいちゃんの写真を懐にしまった。白く、わずかに尖った歯がちらりと見える。相変わらずきれいな歯だな、と思う。
ハロ、という名前は、じいちゃんが付けたらしい。付けた、というか、成り行きでそうなった、というか。金髪に赤い目をしたハロを外国人だと勘違いしたじいちゃんが、ハロー、と声をかけたから、ハロ。弥太郎は変なやつだったよ、というのが、ハロの口癖だった。ふつうの人間は、僕を見たら恐れをなして逃げ出すっていうのに、弥太郎は平気で声をかけてきた。そのうえ、ハロー、だ。ふざけてる。
ふざけてる、というわりに、じいちゃんの話をするときのハロの顔はいつも優しかった。今だってそうだ。写真に触れる手つきも、そこに映る自分たちを見つめる目も、あきらかにおれに向けられるそれとは違う。それがどうしてか、なんて、当たり前にわかる。おれと同じだ。おれもハロも、恋をしている。決して叶わない、ばかみたいな恋を。