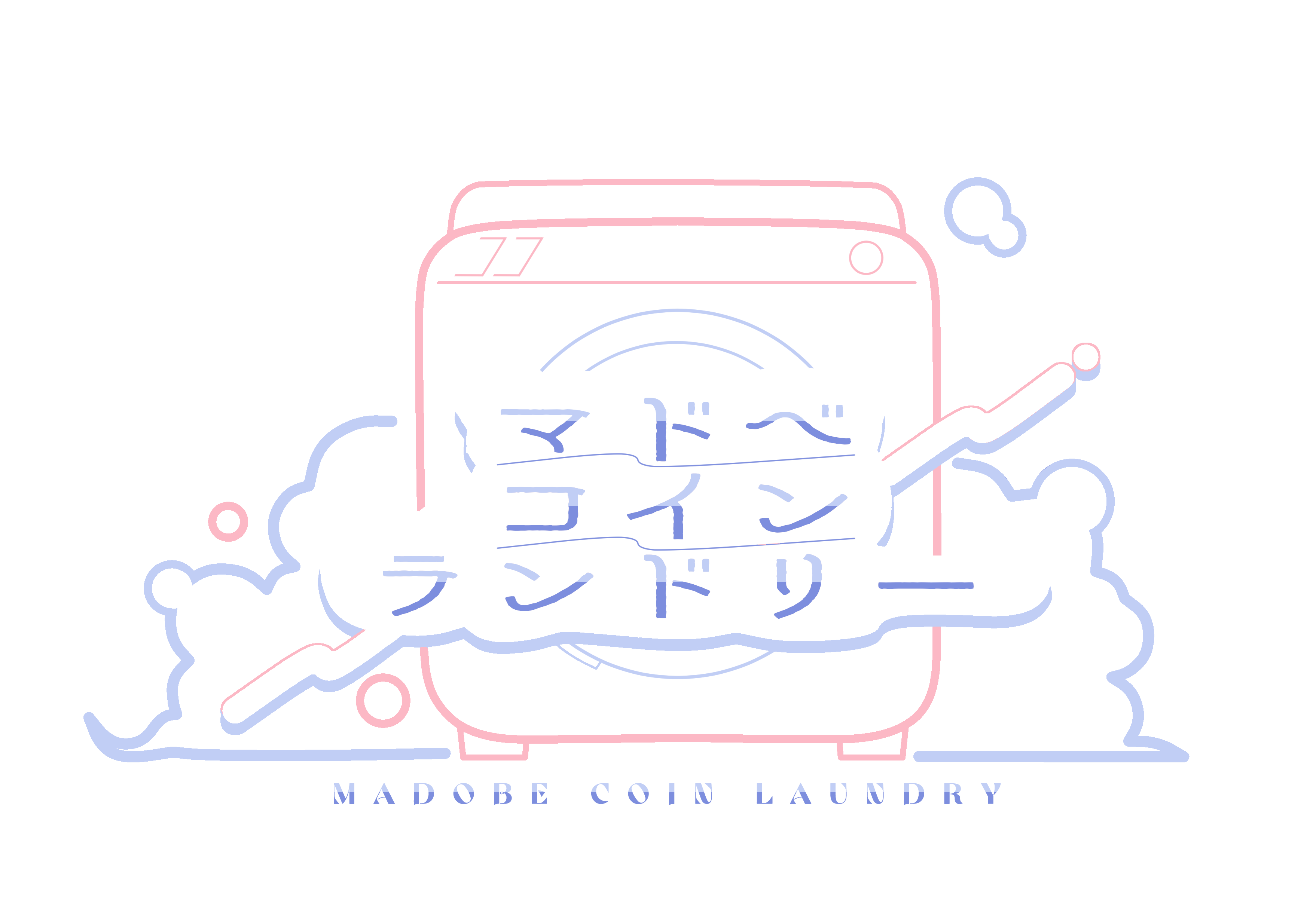あなた今幸せですか、というのは、どうやらテレビによって生み出された架空の宗教勧誘のイメージだったらしい。この部屋には今悪い氣が漂っています! と自信満々に言う、年齢不詳の女性の話に適当な相槌を打ちながら、そんなことを考える。本当にいくつなんだろう、この人。三十代にも見えるし、六十代と言われても納得はできる。この年齢を曖昧にさせる雰囲気が彼女の言うところの氣とかいうやつによるところなら、案外信頼に値するのものなのかもしれない。実際、悪い氣が漂っているというのも、あながち間違いではないのだし。
「おーい、清春。早く来ないとラーメン伸びるぞ」
「わかってる」
背中を反らして、リビングに向かってそう叫ぶ。目の前の女性がびくりと体を震わせる。すみません、いきなり大きい声出して、と形式ばかりの謝罪。彼女の驚きが、大きな声に対してではないことは、ぼくが一番よくわかっている。
「あ、ええ、はい。ですからですね、このヒーリングセラピーに参加することで」
驚きつつも勧誘を続けるその姿勢には、若干の感心すら覚える。とはいえ、今のぼくにとっては、ヒーリングセラピーよりもラーメンのほうがよっぽど大事だった。せっかく奮発して、高い袋麺に叉焼まで入れたのだ。
「そういうの大丈夫なんで」
やんわりとそう言って、それから、少し考える。そのまま扉を閉めても、べつによかった。この人だって数打ちゃ当たる戦法でぼくの家に訪ねてきただけで、無理やり扉を開けようとしたり、何度もインターホンを押すほどの執着が、ぼくにあるわけではないだろう。だからこの女性を追い返すには扉を閉めるだけで十分効果的で、だけど今のぼくはなんとなく、余計なことを言いたい気分だった。
「なんだった?」
部屋に戻ると、拓がさっそくそう聞いてきた。宗教勧誘、と苦笑いをしながら机の前に座る。ラーメンからはまだ仄かに湯気が立ち上っていた。
「あー、あなた今幸せですか? ってやつ」
「ぼくもそう思ってたんだけど、違ったんだよね。悪い氣が漂ってますみたいなこと言われた」
拓は一瞬目を丸くして、それから心底愉快そうにけらけらと笑った。合ってるじゃん、と拓が言う。悪い氣、の張本人のわりには、呑気な笑い方だった。
「それで?」
拓が楽しげに言う。ちゃんと、地縛霊が住んでますって言った?
地縛霊なんだよね俺。そう拓が明るく笑って言いのけたのは、ぼくが引っ越してきた初日のことだった。昔ここ住んでて、死んでからも離れられなくてさ。軽やかにそういう拓は、幽霊がつけているような三角巾もつけていなければ白い服でもなくて、それでもしっかり、全身がうっすらと透けていた。ぼくが子どものころに、地縛霊の猫が出てくる妖怪のアニメが流行った時期があったけれど、まさか自分が引っ越した部屋に地縛霊がいるとは、小学生のぼくは考えもしなかっただろう。
とりあえず、事故物件のわりには家賃が高いな、というのがぼくの第一の感想だった。
「言ってないよ。頭おかしいと思われるし」
「実際おかしいけどな。地縛霊とけろっと一緒に飯食ってるやつは」
「失礼だな」
こういうときに一番効果的なのは、とにかく美味そうに食事をすることだった。拓は幽霊なので、当然食事はできない。そういう存在の前で、美味しそうに食事をするのは、相当効くらしい。あーうま、とラーメンを啜りながら呟く。実際は大して美味しくはない。奮発したわりには、という感じだ。一人で食べたら、きっともっと味気なかったことだろう。
性格悪ぃ、と拓がぼくを睨む。
「ひどいこと言うな。本当にぼくの性格が悪かったら、さっきのおばさんに頼んでさっさと君を除霊してもらってるよ」
「そういうのできるのかよ、宗教勧誘って」
「さあ、でも悪い氣って言うくらいだから、追い払うブレスレットとかはくれたのかもね。法外な値段のやつ」
肩をすくめる。なけなしの給料でそんなものを買わされたらたまったものじゃない。
「で?」
「うん?」
「なんて言って断ったんだ? 清春は。まさかガン無視して扉閉めたわけじゃないだろ」
それでもよかったな、と少しだけ思う。勝手な決めつけでぼくの中に土足で踏み込んでくるような人間には、そのくらいやってもよかったのかもしれない。
とはいえ、実際のぼくにはそんな攻撃性はなく、ただやんわりとした拒絶に、余計なひと言を付け足しただけだった。まあ適当に、と曖昧な答えを拓に返す。拓はふぅん、と相槌を打つと、それ以上はなにも言ってこなかった。拓のこういうところを、ぼくはわりと気に入っている。
ラーメンを一口啜る。微妙だなと思っていたけれど、麺とスープをしっかり絡めると、案外悪くはない味だった。