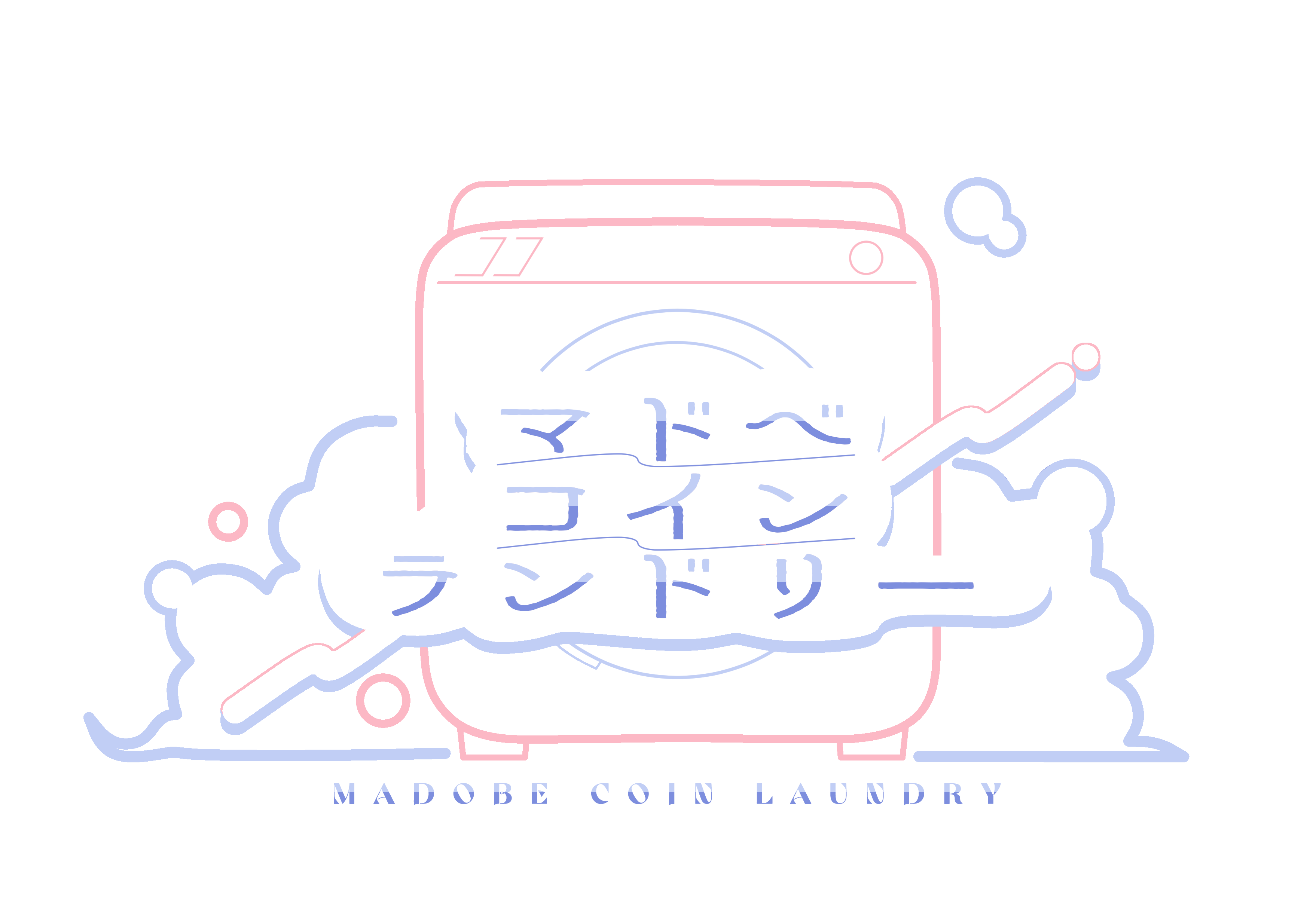なぜ僕には友達がいないんだろう、と國光さまが唐突に言ったのは、食事を終えて部屋に戻られてからすぐのことだった。少し困惑しつつ、いらっしゃらないのですか、とおうむ返しに聞く。まあいないだろうな、というのが本音ではある。この世間知らずのおぼっちゃまが、同年代とキャッキャうふふと戯れているところなんて想像もつかない。案の定、國光さまは神妙な顔で首を縦に振った。
可哀想だとか、そういう同情よりも先に、なぜ今さら、という感想がまず浮かんだ。國光さまの世話係になってから三年ほどが経つが、このわがまま放題のクソガキに友人がいる気配なんて感じたことがない。今までの國光さまがそれを気にしている様子もなかった。
「お父さまに心配されたんだ」
おれが問いかけるよりも先に、國光さまは理由を口にした。ああ、なるほど、と思う。確かに年頃の息子の口から、ほとんど友人の話を聞くことがなければ、まともな親ならば心配するだろう。気づくのが遅かったような気もするが、光秀さまほどの多忙な人間であれば仕方はない。
「……友人など、いなくてもどうとでもなりますよ」
國光さまにはお友達がいらっしゃるじゃないですか、なんて嘘はつけないので、とりあえずそう口にする。実際、國光さまほど恵まれた環境にあるのであれば、同年代の友人の有無なんてどうってことはないだろう。適切なコミュニケーション能力は損なわれるだろうが、それを補って余りある権力が、この家にはある。
「でも桐野。おまえだって、大学時代には友人のひとりやふたり、いただろう」
「……まあ、いましたね」
実際にはひとりやふたりの話ではない。残念ながら、おれはこのクソガキとは違って人当たりがよく、コミュニケーション能力に長けているのだ。友人の家で鍋パをしたことも、オールで麻雀をしたこともある。ほらぁ! と國光さまが非難するような声で言う。
「桐野の裏切り者!」
「裏切るだなんて、そんな」
めんどくさいガキ、と声には出さずに思う。仕事でなければ声に出していた。
おれに友人がいて、自分には友人がいないという事実は、どうやら國光さまのプライドを傷つけたらしい。恨めしそうな目が、じっとおれを見つめている。なんて面倒な。これのご機嫌取りをしなくてはいけないんだから、つくづく厄介な仕事だ。
少し考えてから、國光さま、とその不貞腐れた横顔に声をかける。どうしたリア充の桐野、と國光さまが不満げな声で言う。どこで知ったんだろうか、その言葉は。
「お言葉ですが、國光さまには本当にご友人が必要なのでしょうか」
「必要だろう。お父さまが心配する」
「では、光秀さまは具体的にどのようなことを國光さまに望まれていると思いますか?」
「それは、友人と出かけたり……食事をしたり……?」
國光さまのふわふわとした友人像に思わず笑いそうになる。ろくに友人ができたことがないと、人はこうなるのか。しかし、國光さまのイメージする友人がそれであるのならば話は早い。要はこのガキは、遊びに行く相手が欲しいのだ。
少々お待ちを、と國光さまを待たせ、スマホを操作する。適当な飲食店、適当な映画。少しラフなセレクトすぎる気もするが、今回はこのくらいがちょうどいいだろう。
「桐野、なにを?」
「週末の映画とレストランを予約しました。出かけて、食事をしましょう」
「おまえは友人じゃないが」
「ええ。ですが、光秀さまも少しは安心なさると思いますよ」
実際、そう歳の離れていないおれが國光さまの世話係に選ばれたのは、國光さまの友人代わりになれるようにという光秀さまの思惑であると耳にしたこともある。過保護な親だ。
それもそうか、と國光さまが頷く。まだ微妙に釈然としていなさそうな顔ではあるが、一応は納得してもらえたらしい。きゅっと寄せられたその眉根を見ていると、なんだかむかついてきた。
出かけたり、食事をしたり。笑ってしまうくらい陳腐な友人のイメージ像だ。そんなのは、ぜんぶおれでいいはずだ。どうせこのガキのわがままに耐えられるのなんて、この世でおれしかいないのだから。ああ、腹が立つ。本当はなにひとつそうじゃないことに、腹が立つ!
大丈夫ですよ、となるべく穏やかで優しい声を作り、國光さまに言う。友人ができたときの予行練習だと思いましょう。そう、思ってもいない言葉を口にしながら、おれは静かに、炎のような怒りを腹の奥底へとしまい込んだ。