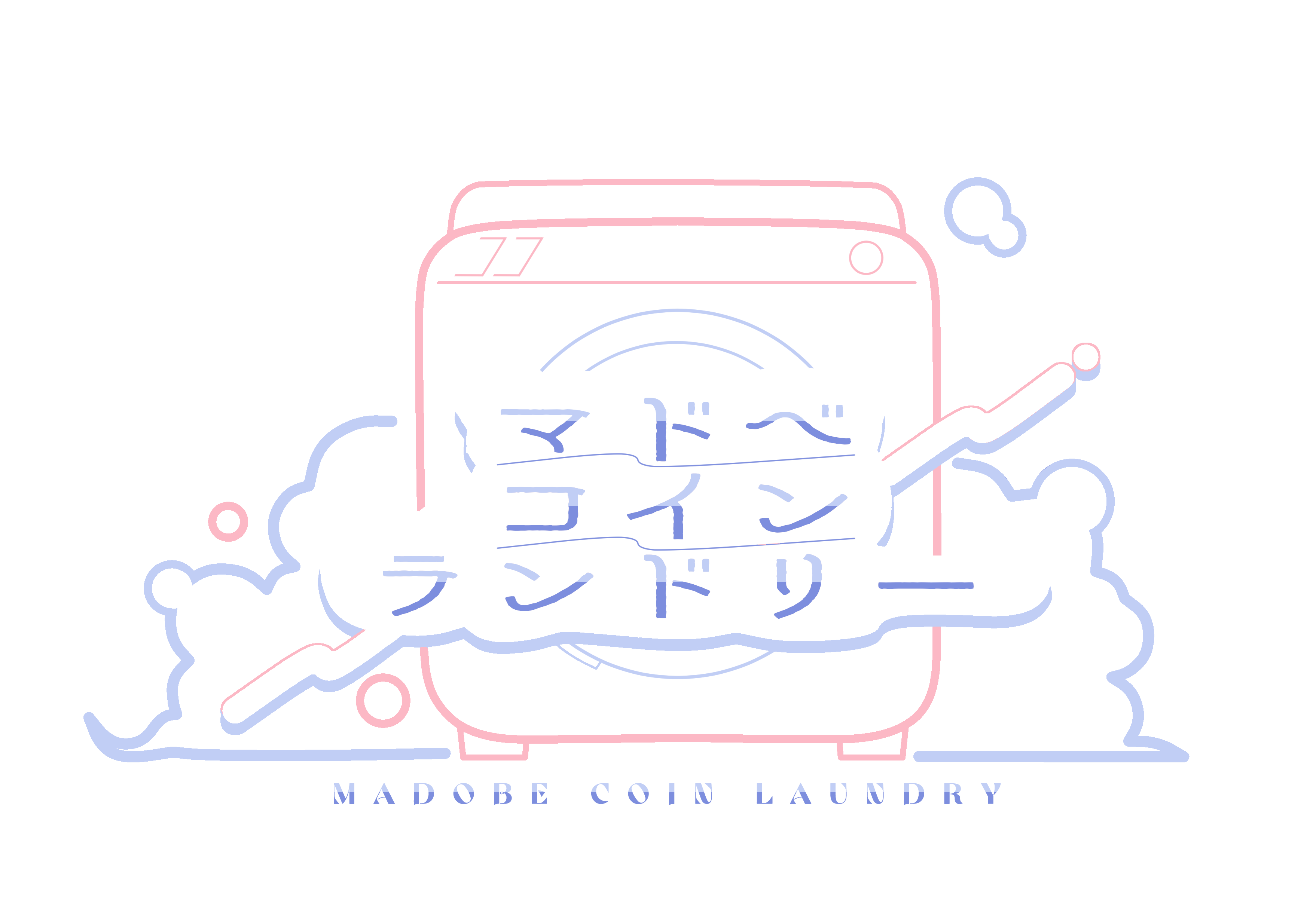透は今日から、うつわに入って生活することにしたらしい。透、というのはぼくの恋人の名前である。もともと小柄な子だったけれど、まさかうつわに入るほど小さくなるとは、ぼくも思ってもいなかった。こういう少女漫画が、昔あったような気もする。もっとも中に入っているのは、少女漫画には出てきそうもない、仏頂面のサラリーマンなのだけれど。
「現実に嫌気がさしたんだ、僕は」
十五センチほどの白くてつるつるしたうつわの中で、透は不機嫌そうに顔をしかめて言った。
「だからって、うつわの中にひきこもるかなぁ」
「いいだろ、別に。小さくなってやったんだから迷惑はかけてない」
「迷惑ねぇ」
苦笑いをしつつ、うつわの中の透を見つめる。つい数日前まではいつも通りの透だったのに、いったいどうしてこんなことになってしまったんだろう。なんでこうなったんだろうねぇ、と呟くと、透はしかめ面をますます歪ませて、こら敏郎、と言った。敏郎、とはぼくのことだ。
「考えても仕方ないだろ、そんなことは。そんなことより旅行だ。こんな姿じゃ仕事にも行けないからな。車を出せ敏郎」
「透は仕事がなくても、ぼくには仕事があるんだけど」
「休め、そんなものは。お前には休みが必要だ」
透に言われたくないよ、とぼそりと呟く。透は絵に描いたような社畜だった。
とはいえ、ぼくは透にさからえない。たとえ小さかろうと、うつわにひきこもっていようと、それはぼくが透をないがしろにする理由にはならないのだ。ぼくにとって、透というのはそういう存在だった。
そういうわけでぼくは、うつわの中でえらそうにふんぞり返る恋人と旅に出ることになった。車内のBGMはクイーンが良いと透が言ったので、透がぼくの車の中に置き去りにしていたクイーンのアルバムを流した。
旅行は楽しかった。道行く人はぼくらを奇異の目で見たりしたけれど、残念ながらぼくも透も、奇異の目には慣れている。
会社に休みの連絡を入れたのは最初の一日だけだった。なんだかぜんぶどうでもよくなってしまったのだ。それはたぶん、うつわの中の透も同じだった。透は旅行の間、うつわの中でよく笑った。睡眠不足とストレス過多で常に苛立っているような透が笑っているところを見るのは、ずいぶんとひさしぶりだった。
山に行き、何泊かして、山に飽きたら海に行きまた何泊かして、そういうことを何度か繰り返した。行き先はいつも透が適当に決めた。透が決めたのなら、辿り着くのがどこだって些末な問題だと思った。ぼくは少し日に焼けたけれど、透はずっと真っ白なままだった。
「次はどこへ行こうか」
食事を済ませて車に乗り込み、ぼくは透にそう聞いた。透にその質問をすることにも、すっかり慣れ切っていた。
「北がいい? それとも南?」
「北」
透は淡々とそう言った。透の言うとおりに、車を発進させる。右、左、左、直進して右。方向を指示する以外の時間、透はずっと黙っていた。静かな車の中で、クイーンだけが鳴っている。そのうち見たことのある道に辿り着いて、そこでぼくはようやく気が付いた。解像度の低いカーナビの日付は、透がうつわにひきこもるようになってから四十九日が経つことを教えてくれていた。うつわ。白くてつるつるした、骨を入れるためのうつわ。
車は墓へと向かっていた。ねえ透、と名前を呼ぶと、透は黙って、うつわからぼくを見上げた。名前を呼んだのはぼくのくせに、なにを話せばいいのかわからなかった。ぼくは透に、たとえば食べたい料理だったり、遠くまで行ける足だったりを与えることはできるけれど、言葉はなにもあげられない。張り詰めたところにいる透に、届く言葉がわからない。それはきっと正しいことではなくて、だから透は死んだのだろう。
無言のままで、ぼくは休憩のために、車をサービスエリアに止めた。車の窓から差し込んだ人工のひかりに、透はまぶしそうに目を細めながら言った。楽しかったな、旅行。
「うん」
うん、ともう一度言う。そうだね、楽しかった。ぼくの言葉に、な、と透は笑ったあと、なあ、ガム買って来てくれよ、と言った。サービスエリアに売っている眠気覚ましのガムが、透は昔から好きだった。運転手はぼくなのに、はたして透が眠気覚ましのガムを買う意味があるのかとずっと思ってはいたけれど、ぼくは結局毎回ガムを買いに行かされていた。ぼくは透にさからえないのだ。ずっと、ずっと。
売店でガムを買って、冷たい駐車場を歩く。車に戻っても、あの白いうつわの中からはもうなんの声もしないのだろう、となんとなく思った。透の笑い方は、そういう笑い方だった。
小説「透はうつわの中」
投稿者:
タグ: